「半分サラリーマン型」が普及するとき

|
| 『米国製エリートは本当にすごいのか?』 |
この本は「スタンフォード留学の2年間で5人しかかわいい女性を見なかった」といった個人視点による政治的に正しくないマイニュースが随所に面白いのだが、突然でてくる日本の労働市場の具体的な話も興味深い。→『米国製エリートは本当にすごいのか?』
まず、今後は「半分サラリーマン型」の契約記者・編集者が徐々に広がっていく、との予想についてであるが、これは「経営層」と「資本」のいずれか(または両方)が変わらない限り、難しい。
日本メディアの編集長→編集局長→担当役員→社長という経営層のライン系キャリアパスは、全員が100%サラリーマンで、優秀なフリーがヘッドハンティングされていきなりトップに就くことはない。
十年一日のごとく、新入社員のときから同じ会社にいた人間がライン長につき権限を握っているのだから、新しい発想は生まれない(だからイノベーションが起きず衰退の一方なのだ)。
資本のほうは、さらに変化の見込みがなく、ルパードマードックが毎日新聞あたりを買収でもしてくれれば変わるだろうが、投資先としての魅力が全くないので、今後も変わらないだろう。
したがって、
|
といった「半分サラリーマン型」の契約記者・編集者は、今のパラダイム下では実現しない。「おれも昔はそうだった」「そんな虫のいい話はない」というのが日本企業のムラ社会的発想で、「うちの名刺を使う以上、専属以外ありえないだろ」でおわり。

|
「ジャーナリストがサラリーマンを卒業するとき」 |
すでに現在でも、専属契約の社員は普及していて、編集部30人中15人ほどが契約だという『SPA!』をはじめ、『週刊文春』『週刊現代』などの週刊誌は記者・編集者の半数程度が契約社員で、いつでも不要になったらクビを斬れる。違いは会社の名刺を使って他のフリーの仕事をしていいかどうかだが、これを会社が表向きに認める可能性はゼロだ。取材先とのトラブルになるだけだからである。
半分サラリーマン型に続く2つめの働き方として紹介されているのが、エース級の人物を専属契約で囲い込む形。
|
これに相当する稼ぎを実現したジャーナリストは、日本でいうと筑紫徹也氏と田原総一朗氏くらいだが、どちらもテレビ人で、活字世界で囲い込まれたスターといえば、かつて朝日新聞に囲い込まれた夏目漱石(エリート銀行員の初任給が月35円の時代に年収3600円の契約だったという)くらいだろう。
今、多額の報酬を払える体力がある媒体といえば、朝日、読売、日経、そして大手出版社くらいのものだが、たとえば勝間和代氏に1年間、専属的に仕事をしてもらう代わりに年間2~3千万円払う、といった発想は全く湧き出てこない。合理的に考えると部数は伸びて売上増が見込めるから、投資対効果を考えれば十分にありうる選択肢ではあるが、一言でいえば「ひがみ」根性が根底にあって、経済合理性では意思決定されないのだ。
比較的に自由度が高めな雑誌の世界では、かつては立花隆氏が『週刊文春』や『週刊現代』で、優秀な社員スタッフチーム付きで年間1千万円超の原稿料で連載していた時代もあった(『田中角栄研究』『同時代を撃つ!』など)が、もはや自社社員の給与水準を維持するために外部からコストを削っていく、という流れは不可避となった。社員のバカ高い給与を守るために、媒体のジリ貧を容認する、という緩慢な自殺の過程を選択しているのだ。
講談社や文芸春秋などは無駄な人件費の宝庫であり(この事実については内部の社員ほど反論できない確定的な事実)、リストラさえすれば立花隆クラスの5人や6人は簡単に囲い込むだけの体力があるので、いくらでも改革の余地はある。労組と刺し違える覚悟を持った経営者のリーダーシップと経営判断1つで、ダントツ1位の雑誌を作れてしまう。だが、自殺過程に入っている出版社はやる気がない。これも経営判断だ。やはり、資本と経営が入れ替わらない限り、スタープレーヤー契約もありえない。
つまるところこの先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り122字/全文2,127字
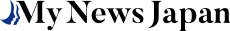
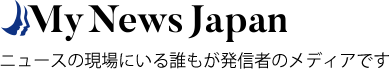


Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報