PASMO Suica、盗難防止ゲート…安全基準値違反が続出 電磁波の甘い規制

|
| 3月18日からはじまったPASMOの改札。光っているカード読み取り部から電磁波が常時、発生している。 |
- Digest
-
- PASMO、Suica改札で国の基準を超える電磁波
- 盗難防止ゲートでは鍋が過熱
- アメリカではペースメーカー使用者が失神
- スーパーや図書館職員は知っているのか
- 総務省「たぶん経済産業省が管轄…」
PASMO、Suica改札で国の基準を超える電磁波
3月18日から東京では、私鉄や地下鉄、路線バスに共通で使えるカードPASMOのサービスがはじまった。JR東日本のSuicaと同じく、ICカードを使った乗車券システムだ。SuicaとPASMOは相互利用できる。
仕組みとしては、改札のカードの読み取り部から電磁波を発生させ、乗客がカードをかざす1秒ほどの間に、運賃精算などの情報をやり取りするというものだ。使用している電磁波は、AMラジオ放送より少し高い周波数(13.56MHz=メガヘルツ)のもの。ためしにAMラジオを近づけてみると、読み取り部付近では強いノイズがでた。
注:ラジオのノイズによって確認できる電磁波は、一部だけなので、ノイズが出ていることで電磁波が出ていることは確認できるが、ノイズがないから電磁波は出ていないということにはならない点にご注意願いたい。
電磁波の強さは、発生源(放送局の場合であれば発信アンテナなど)の近くが一番強く、距離が離れるに従って弱くなる。放送局のアンテナの周辺に人が立ち入らないように柵がめぐらされているのは、電波法で人体防護のための基準が定められており、電磁波の強さが基準値以上の場所には人が立ち入れない措置をとるよう決められているからだ。
一方、PASMOやSuicaの手をかざす改札の読み取り部も電磁波の発生源であることに変わりはないが、現状の法律は事実上、テレビやラジオといった無線局のみを対象にしているため、完全に野放しになってしまっている。実際には、発生源近辺の電磁波の強さは、かなり強く、その部分に毎回手をかざさなくてはいけないわけだ。体の一部分だけとはいえ、毎日改札を通るたびに強い電磁波にさらされることになる。

|
| 上:JR東日本中央線の梁川駅(無人駅)のSuica改札での電磁波測定。磁場の値は0.8730A/mを指している。基準値(0.16A/m)の5倍以上の値だ。 下:実測の結果と国際ガイドライン値、国内の電波防護基準値の比較  |
では、どのくらい強い電磁波が出ているのか。実際に、JR東日本中央線の梁川駅で、Suicaの改札のカード読み取り部を測定してみた(右記参照)。日本国内の防護基準では、0.16A/mと定められている。だが、実際の読み取り部での値は、防護基準の5倍以上になる0.87A/mという値だった。
電磁波の安全基準としては、国内の防護基準のほかにも、より厳しい国際的なガイドラインも存在する。国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)という機関が定めるガイドラインだ。この国際的なガイドラインでの基準値は、0.073A/m。Suicaの改札部は、なんと12倍という強さである。
確かに、基準値を超えているのは、読み取り部から数cmくらいの範囲だけ。改札全体が強い電磁波で覆われているわけではない。しかしその基準値を超えている部分に手をかざさないと改札を通れない。これまでの磁気式のカードや切符の場合は、改札機の中に取り込んでから磁気データの処理をしていたので、乗客が、体の一部とはいえこのような強い電磁波にさらされることはなかった。
電磁波の値の読み方(電磁波と電場、磁場について)
電磁波とは、「電場」と「磁場」の振動(波)のこと。したがって電磁波の強さに対する規制は、電場と磁場それぞれの基準が定められている。 また基準値は、周波数によって値が変わる。
SuicaやPASMOの場合、基準値を超えたのは磁場だ。基準値を超えているのは読み取り部から数cmの範囲だが、そこに手を近づけなければ改札を通れないという仕組みになっている。電場は、国内の基準値と国際ガイドライン値の間くらいという値だった。
ちなみにアンテナから遠く離れたところでは、電場と磁場の強さは関連があるので、片方を測ればもう片方の値も計算できる。しかし発生源から近い場所では、そこから発生する磁場と電場がそれぞれ独立しているため、それぞれ個別に測る必要がある。
現在の国や国際的な基準値を超えるということが、どれだけ危険性を含んだものかを説明させていただきたい。
そもそも日本の防護基準や国際的なガイドライン値は、発ガン性などの影響は、科学的根拠が不十分としてまったく考慮していない。ではどういった影響を前提にしているのかというと、かなり強い電磁波にさらされた場合、体内で電流が流れて感電するとか、または、電子レンジのように、熱が発生し体温が上がるといった影響しか認めていないのだ。
現在、電磁波の発ガン性の証拠として一番はっきりしているのが、送電線などから発生する50Hz、60Hzという周波数の電磁波(特に磁場)による小児白血病リスクの増加だ。世界中の疫学調査で はっきり示されている。この50Hzという周波数での国際ガイドライン値(1000mG)に対して、この小児白血病のリスクが増えると指摘されているのは4mG。なんと1/250という値なのだ。
注)日本の防護基準では、送電線の周波数は低域であるために、基準値がそもそも存在しない。これは総務省が、実際に無線や放送用の電波として使用されている周波数=10kH以上の周波数(ラジオやテレビ放送、携帯電話、SUICAやPASMOの電磁波も周波数帯としては含まれている)だけを対象にしているため。
ガイドライン値の1/250の弱さでも発ガン性の証拠が認められつつある状況が一方であるのに、SuicaやPASMOの改札部分での電磁波の強さは、その国際ガイドライン値や、それよりさらに甘い国の基準値を超えているわけだ。
このような機器が、何の安全性の検証も行なわれないままに、私たちの日常生活に増えてきているのである。
盗難防止ゲートでは鍋が過熱
PASMOやSuicaよりももっと強い電磁波を広範囲に発生させている装置がある。図書館やスーパーマーケットの入り口に設置してある盗難防止ゲートだ。
盗難防止ゲートには、いくつかの種類があり、使われている周波数も多岐にわたる。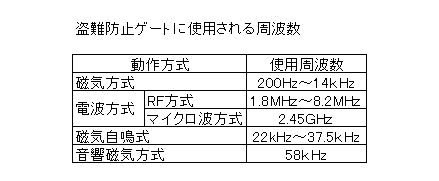
外観では、どの周波数が使われているかは分からない。
その中の磁気方式で14kHzという周波数を使っている住友3M社のM-3810というゲートの磁場を実際に測定してみた結果が、下の図だ。
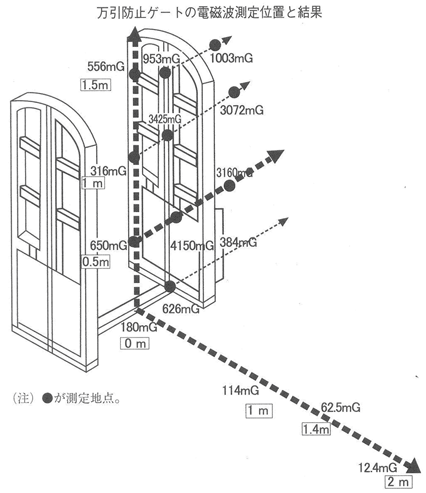
【出典:「しのびよる電磁波汚染」(コモンズ刊 2007年2月)】
ちなみにこの周波数での国際ガイドライン値は62.5mG(ミリガウス)。ゲート周辺1.4mの範囲内はこのガイドライン値を超えている。またこの周波数での日本の基準値はかなり甘くて910mG。ゲートから数センチのところでは、この日本の甘い基準値さえ超えている。ということは、電波法に照らし合わせれば、ゲート自体を柵で囲んで、人が近づけないような措置をとる必要があるということになる。
SuicaやPASMOより厄介なのは、体の全身が強い電磁波にさらされることになるところだ。

|
図書館ゲートの枠上に鍋を置き、鍋に温度計をつけて熱くなるか調べた。数分で鍋の温度は84℃まで上昇。素手では熱くても持てないほどになった。 |
また、14kHzという周波数は、実はIH調理器に使われる電磁波に近い。ためしに、ゲートに鍋をのせてみて、鍋が加熱するかどうか実験してみた。
すると、ものの数分で鍋の取っては84℃にまで上昇、素手でもてなくなった。
アメリカではペースメーカー使用者が失神
送電線の近くで小児白血病が増え、携帯電話で脳腫瘍が増えている可能性が指摘されている 状況で、常にゲート近くで働いている店員や図書館職員の人たちにガンの発症率が増えないと言えるのだろうか。
2002年には盗難防止ゲートを導入した図書館で、職員の人たちに頭痛やめまいなどの症状がでたという記事がアエラに掲載(2002年12月2日)された
この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り3,252字/全文6,520字
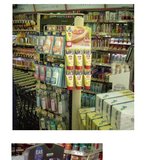
街で見かける盗難防止ゲート。広告が張られたり、ゲート周辺に商品が山積みされたり、ゲートに商品がつるされていたり。それらのゲート付近を測定してみると、すべて国際ガイドラインの400%(4倍)を超えていた。(東洋メディック社輸入元のEFA-300という測定器を使用。表示の数値は国際ガイドライン値の何%にあたるかを表示)




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
図書館スタッフやっています。
図書館での電磁波の記事はゲートの話が多いですが、磁気入れ装置(カウンターブックチェックユニット)はどうなのでしょうか。カウンター業務ではその装置のすぐ近くにずっと座っているのですが、どれくらい危険か知りたいです。
植田さんの著書(2007年2月の発行)で電磁波のWEBを開設するとありました。いつオープンですか?
14kHzのデータが載ってますが、その他の周波数のデータは揃っているのでしょうか?
しのびよる電磁波汚染に載っているのでしょうか。参考にしたいのですが。
先日PASMOと携帯を持ち改札を通過した際に感電したような痺れが走りその後気分が悪くなりPASMOを持っていた方の指先が未だに痺れと腫れが収まらない状況ですが電磁波に関係しますか?病院では感電特有の指の内部が火傷している状況だとの診断を受けていますが如何思いますか?
大学にある図書館のゲートは確かにひどいです。まずピーという音が5m離れてても聞こえる。ヘッドホンをしたままだと強力なノイズが鳴る。身体への影響は専門でないため言及できませんが、実感として強い電磁波があるように感じます。
電磁波について脳神経外科医からメッセージをもらいました。今から20年以上前に電磁波が生体に与える影響に関する文献を集めました。すでに、レーダーはじめ、種々の機器の電波を多用していた西側には、そのような研究で表に出ているものはほとんどありませんでした。(下記に続く)
ほとんどが、携帯電話その他の文明の利器の開発に立ち遅れた東側の論文でした。「携帯電話で脳腫瘍」というのも当時からありました。ここ30年間での携帯の世界的発展の割りに、悪性脳腫瘍が増えたと言うことはありません。
前回のケータイの記事で、掛園さんのコメントに対して「電磁場の変動が波動として空間中を伝播するとき、これを電磁波という」というコメントがされていますね。それで良いんじゃないでしょうか?電磁波=電磁場で有害なのはX線や紫外線ばかりではないのではということが今問題になっているのですよ
電磁波で身体に有害なのは波長の短いガンマ線、X線、紫外線です。PASMOからはこれらの波長の短い電磁波はでていないはずです。
総務省の調査結果や、見解などがちゃんと取材されていますね。有料部分ですが。
せめて厚生労働省の「医薬品・医療用具等安全性情報」と総務省の「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」ぐらいは…
>総務省は無線局でないなどの理由で>野放しにしている。そうですか?確認の取材をされました?この種のPASMOなどは電波法にいう小電力機器もしくは特定小電力機器としての条件を満たせば、個別の無線局としての認可は不要、という規定になっているはずです。総務省が野放しにしているのではなく、特定の条件を満たすものとして認めているのです。
些細な点ですが,AMラジオ放送は約0.5MHz~1.6Mhz。で,13.56MHzはかなり高い周波数です。AMラジオ放送は中波帯,13.56MHzは短波帯です。
記者からの追加情報
会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい
新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)