読売が紙面で“税金もっとよこせ” 公共紙面広告だけで税金8億円無駄の試算も
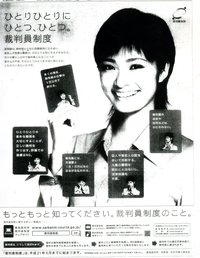
|
| 最高裁、法務省、日弁連が共同で出した裁判員制度の新聞広告。経費のもとをたどれば税金である。 |
- Digest
-
- 政府広報で税金8億円が無駄の可能性
1月19日付け『読売新聞』に、「政府広報紙不足で申し入れ」と題する記事が掲載された。薬害C型肝炎の原因である血液製剤の納入先を明記した政府広報(折込チラシ)が「新聞購読家庭に行き渡らず、厚労省などに問い合わせが殺到している」ので、読売新聞社が「十分な量の政府広報を用意することを政府に求めるよう、日本新聞協会に申し入れた」というのだ。
つまり読売は、自分の紙面で堂々と、「政府広報(=国民の税金)をもっとよこせ」と求めているのだ。
全国で戸別配達されている新聞の公称部数は、約4500万部。従ってこれらの新聞すべてに政府広報を折り込むためには、同じ部数の政府広報が必要になる。ところが実際に政府が準備した政府広報は3000万部で、約1500万部(33%)が減数されていた。読売によると、それが原因で内閣府に「問い合わせが殺到」したというのである。
いったい何本の電話を根拠に「殺到」と表現しているのか数字も隠されているため、読者は読売の政府に対する“営業活動”を鵜呑みにしてはいけない。読売は、折り込みが足りないというなら、まずは自社の本当の実売部数を公表すべきだろう。

|
山積みになった「押し紙」。新聞で包装されているのは折込チラシの束。定期的に古紙回収業者のトラックで回収される。写真は記事とは無関係。 |
実際、実売部数についての検証は進んでおり、新聞社が新聞販売店に搬入する新聞のうち、かなりの新聞が実際には配達されず、ノルマとして買い取りを強いられる「押し紙」に化けている実態が分かってきた。後述するように、読売西部本社管内では推定4割にもなるため、公称より33%減らしても、まだ余るのだ。
その結果、内閣府も政府広報を新聞に折り込むに際して、適正な折込部数を決めるのに苦慮しているようだ。内閣府の職員が言う。
「水増し部数があるという話は聞きますが、地域によって程度が異なり、把握しようがないのが実情なんです」
内閣府は「押し紙」を推定して1500万部の減数をおこなったことを公式には否定するが、部数の水増しが行われていることを把握しているのだから、やはり「押し紙」を考慮して、公称部数を33%下回る数量を設定したと考えるのが自然だ。
政府広報の部数が3000万部と4500万部では、経費の支出額が大幅に異なる。しかも、その経費は国民の税金だ。
C型肝炎の政府広報に割り当てられた予算は、約5億円。もし、内閣府が「押し紙」分を含めた4500万部分の政府広報を準備していたとすれば、1億円から2億円ほど余計に税金が支出されていたことになる。
◇「押し紙」4割のYCが続出読売新聞の西部本社管内(九州・山口地方全県)における部数水増しの実態を紹介しよう。広告主が、いかに騙されているかを実感できるはずだ。
次に示すのは、福岡県の筑後地区とその周辺地域におけるYC(読売新聞販売店)で明らかになった、水増し部数、あるいは「押し紙」の実態である。
※YC大牟田明治: 2007年10月の定数は2400部だった。しかし、弁護士の仲介で「押し紙」を排除したので11月の定数は1480部になった。差異の約900部がほぼ「押し紙」だ。
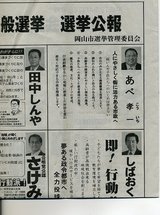
|
新聞折込の選挙公報も、「押し紙」と一緒に多量に捨てられる。写真は記事とは無関係。 |
※YC久留米文化センター前:2007年11月の段階で定数は2010部、残紙は997部。残紙の約1000部がほぼ「押し紙」。
※YC小笹:1998年5月の時点で定数が2330部、実配部数が1384部。差異の約1000部がほぼ「押し紙」。
このうちYC大牟田明治、YC大牟田中央、YC久留米文化センター前の3店は、昨年の末に弁護士に依頼して「押し紙」排除に成功した。また、YC小笹は現在、「押し紙」裁判を進めている。
ちなみに「押し紙」の責任がYCではなくて、読売新聞社にあることは、真村裁判を通じて福岡高裁で認定されている。つまり「押し紙」は、読売新聞社による販売政策の結果にほかならない。
これら4店のほかにも「押し紙」があるという話は、複数の関係者から聞いている。
こうした、わたしの多くの取材結果からの推定では、読売新聞西部本社管内の「押し紙」率は約4割である。同じ販売政策の下では、「押し紙」率も平均したものになる傾向があるからだ。従って4割ぐらいの紙面広告が紙面本体と一緒に捨てられている可能性が高い。
政府広報で税金8億円が無駄の可能性
実配部数の不透明な実態は、折込物にかかる経費のだまし取りに加え、紙面広告料金のだまし取りにもつながっている
この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り3,011字/全文4,996字
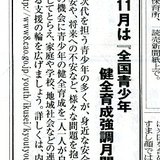
典型的な「突出し広告」スタイルの政府広報




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
政府が準備した政府広報は3000万部
facebookコメント
読者コメント
ABCといい、公取と言い完全に仕事放棄してるな。
何回、読売の押し紙のこと問い合わせしても無視し続けます。調査しようともしません。
しかし、読売はほかの新聞社と比べても突出してお下劣ですね
政権交代で自民政権時代より税金広告が少なくなって文句を言っているように思える。
政治不信もマスコミ不信もなんだか、当り前に思えてきて、小沢が私腹を肥やそうが読売が部数を誤魔化そうが、そりゃやってんでしょ?くらいにしか感じません。つまりこの記事を読んでも「ふーん」くらいにしか思わず、憤慨できない。世の中に絶望した!絶望先生です。
>暗部ばかり
今まで問題にされなさすぎたんですよ。拡張のことでアタマいっぱいなんじゃないですか?ヤクザまがいの詐欺行為や暴力行為が市民から支持を得られるとはとうてい考えられません。
無駄を削除することで新民主党政権は財源をつくります。もちろん、この問題もこれだけ紙の使用の無駄使いをやめないといけませんね。お金だけでなく地球資源の無駄です。
新人所長氏が言ってることは
「ヤクザがニートを立ち直らせている」と言ってるのと同じ。
あまり美化しない方がいい。
美化は紙面だけにして欲しい。
新人所長の言いたいことは良く分かります、読売も渡辺がいるようでは体質は変わらないけど、新人所長みたいな人が多く』現れる事を期待したいですね。
暗部ばかりを無理やりだしているように感じます。残紙の無い店もありますし、ニートを再生させ所長にした方もいます。しかも新聞社は、そんな一青年にお金と時間を用意しています。
バック一つのものがやがて自分の家も手に入れました。こんなこと他の業種で出来ますか?
良いこともレポートしてくれませんか。
もし現在4割の偽装部数が存在するのなら、詐欺販売店のために広告料は4割毀損された状態ということになります。
新聞社の広告局から見ればその販売店や販売局は内部に潜む破壊工作員にしか見えないでしょう。
さらに問題なのは補助は発行部数分で分け合うことになるので、真面目な販売店が割を食う形になります。
加害者を被害者に偽装するのはやめたらどうですか。
紙面広告の場合は'94から'06の12年間で単価が24%下落していて、偽装部数分はすでに織り込み済み。
電通などのマーケティングによって面ごとの接触率を属性別に調べれば、広告主にとって必要な情報は手に入るのです。
単なる破棄率よりも遥かに高度な情報によって相場は決まっている。
広告を出す日本の一流企業はそんなに間抜けじゃないと思いますよ。
広告詐欺、折込詐欺は読売をはじめとする全国紙に限ったことではありません。ある地方紙でも押し紙の損害賠償請求、販売会社の折込詐欺の立件
、県の広報紙の大量廃棄にたいする住民監査請求などをおこなうために準備をすすめている段階です。新聞社のビジネスモデルの崩壊が目前に迫っています。
と言われるのは本当のようで。。(笑)
政治家や役人、民間のサラリーマン、評論家の方々全てが善良でない訳ではないでしょうが、問題の多い難儀な世情ではありますね。
真顔で尤もらしい解説をする政治家と役人,利権に巣食う民間の一部,そして取り巻きの評論家諸氏,「民主主義=衆愚主義」を密かに操作・活用しているのが彼ら「金と権力の亡者」です.右も左もありません.政党も同じ穴の狢.国民は常識的ですが,情報から遠ざけられている為「衆愚」に見えるだけで,斯様な操作をしているのが「彼ら」です.与党,野党の中に存在するかも知れない数少ない志ある方々の奮起をお願いしたいです.
記者からの追加情報
会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい
新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)
企画「まだ新聞読んでるの?」トップ頁へ