健全な社会とは 『13歳のハローワーク』
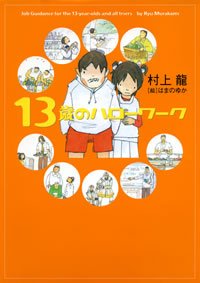
|
村上龍『13歳のハローワーク』の売れ行きが好調だ。5月14日には100万部を突破したことが報道された。《「いい大学を出て、いい会社に入れば安心」という時代は終わっている。好きなことを仕事にして人生を充実させるために》と帯にあり、各学校教育機関が購入したこともベストセラー入りを後押しした。
この本には514の職業が紹介されている。しかし、そこから見えてくるのは結局のところ成功・自己実現のためには職業しかないという固定された価値観だけだ。自分とは何か?という問いに対しての回答は職業だけではないはずだ。
例えば、いま芸術家を目指す人間は少ない。なぜならそれは職業にすることは難しいからだという。ヨーロッパでは素質のある若者にはパトロンがついたり、芸術的素養を伸ばすために国や、企業からのバックアップがつく。しかし、日本ではそれは不可能なことだろう。なぜなら働くことが当然のこととされ、働かず文化的な行為をすることは無駄なこととされる社会だからだ。
働かない、職業から外れることは異質なことだろう。日本では異質なものを排除しようという傾向が非常に強い。それはオウム事件を生んだ土壌をみればあきらかだ。そして社会というものは本来であればそういった異質なものを受け入れる受け皿をもっていなければならない。進路を選ぶ際にも抜け道が多ければ多いほど、その社会は健全で開放されている社会と言える。この村上氏のいうような『好きなことを仕事に』という価値観は、もしそれが仕事にできなかった場合に勝ち組と負け組に別れさせてしまう危険性をはらんでいる。
仕事に興味をもっていなくても、それがその人にとって間違いであるということにはならないはずだ。嫌々仕事をしている人でも、その人の人生が価値のないものだということにはならない。そしてそのことを本当にいわなければならないのは、日本の高度経済成長を支え、好きでもない労働を過酷に続けてきた中高年の世代なのだ。



Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
おすすめの情報を教えてください。
始めてなので
いいまとめなので参考になります
岡山県に「土根性」という名の芋焼酎があるが中々の味ある白芋焼酎でしたぞナ。
日本の酒税法では、麦芽使用率67%さえあれば、他に米・コーン・デンプン・じゃがいも・糖類・カラメルを混ぜてもいいことになっています。これ全てビールと表記できます。これが日本のビールの定義です。
ビールと癌の関係もだが、サントリーとエビスは麦芽と水ぐらいで米とコーンは使っていないはず。ビールの定義がおかしいのでは?このことも是非説明してもらいたいものだ、可能ならばですが。
ビール原料の米は、古くなって食べることもできない農薬栽培されたくず米。 コーンは、遺伝子組替されたトウモロコシを農薬栽培したもの。 糖類・香料・酸味料などは全て化学生産されたもの。 いずれ米にも遺伝子組替米が使われます。 日本の4大ビール会社にオーガニック・ビールは1銘柄もありません。 日本人が一番多く飲むアルコール飲料はビール。 今、日本人の癌患者は2倍以上の増加です。
ドイツ純粋令通りなら安全は間違いないでしょうが、安全な副原料であれば別に問題はないですよね?後は味の良し悪しの問題。ドイツ純粋令準拠以外は駄目、という考え方は極論過ぎると思いますが。
添加物の問題は、非常に根深くイギリスでも過去に砂糖を添加するということが行われていたそうです。何が問題かというと、確かな技術力がなくても、添加物を使うことによって、おいしくなってしまうことが、問題です。混ぜ物なしで造るとまずいものしかできない技術なのに、添加物をいれれば、おいしくなってしまう。使用する原料も本来の作り方より少なくてすむのでしょう。やっぱり本物を私は飲みたいです。
国産ウイスキーラベルに記載されている12とか20などの数字は一番若いウイスキーの年数を表示している??それを誰が裏付け保証するのかなー?国産は熟成義務も負わされていないのに・・それはメーカーの良心を信じる??まさか。お人好しもいい加減にしないと ・・TVCMの狙い・思惑通りの消費者がたくさんいるってわけだ・
エタノールの代謝によってできる、アセトアルデヒドが主な原因です。(他には、アルコールの利尿作用による脱水症状など。)単に、飲み過ぎだと思いますが。
私はもうすぐ40歳になるおっさんですが、この間、つい勢いで発泡酒を2リッター空けちまいました。普段はこんなことはしないので、明日はつらいぞと思っていましたが、ちゃんぽんにしなかったのがよかったのか、なんともありませんでした。私の場合がたまたまかもしれませんし、二日酔いするというのは体質というのもあるのでは?
生ビールの添加物(というか原料)って、米とか澱粉でしょう。二日酔いの原因になるようなものではないと思いますが?イメージだけで判断するのは早計ですよ。
居酒屋で飲む生ビールで二日酔いになるのは、年をとったせいだとばかり思ってましたが、海外で飲むビールは、いくら飲んでも翌朝に残らないので不思議でした。なるほど、添加物が関係あるのかもしれません。なんか納得です。
私は添加物全面賛成論者ではありません。しかしこの記事は大いに疑問です。添加物が入っていると何がどう悪いのか?という説明が全くないまま、批判だけしていますね。味なんか関係なく、添加物のあるなしでしか判断していないだったら添加物の何がどう悪いのかについて具体的に説明するべき。それに安全かどうかを問題にするなら、麦芽やホップの安全性についても明確にすべき
批判的な意見も確かにあると思います。しかし、危険な添加物を使用している食品は、もはや食品と言えないのも事実です。他の会社が添加物を使うから、自社も使うとう悪連鎖を断ち切るには、この本が与える影響は大きいと私は思います。
ただそのことだけを根拠にそれ以外を否定するような論じ方は、先にもあげたようにビールの歴史自体をも否定することにもなりかねません、アメリカでうまれたトウモロコシを副原料にしたライトビールなども、歴史の中で必然的に生まれてきた立派なビールなのです。現在の企業や広告に対しては敏感であるのに、500年前の国家権力に従順なのはいかがなものかと思います。
大袈裟な言い方になりますが、6000年の歴史があると言われるビールに対し、500年前の権力者に決められた定義を鵜呑みにして、原料だけを根拠に批判してしまうのはどうなんでしょう。「ビール本来の原料は麦芽とホップであるが」を否定はしません、ただ歴史の中でビール製造法が淘汰されてベストな形へと導きだされた一つの結果なのです。
そもそも歴史的にみても、雑味を和らげるために、あなた方が悪意をもって言うさまざまな添加物は、ビールをつくるうえで添加されてきました。そのことを考えれば、日本のビール会社が「ビール純粋令」同様に国家に定義された酒税区分をかいくぐって、安く消費者へ提供することからうまれた「その他の雑種」をビールではない、などと非難するよりも、酒税率を都合良く変える国家に対し異議をとなえることの方が筋だと思います。
「1516年にビールの原料は麦芽とホップのみと定義されている」という記述は、バイエルン王のヴィルヘルム4世がビール醸造業者に布告した「ビール純粋令」のことをさしているのでしょう。この布告自体が権力からのもので、アルコール区分を国家が定義しコントロールする為のものであるのに、そこを正当なビールの定義などとしているのは、あまりにも浅はかとしか言いようがありません。
私は書店でウイスキーの項を読んだだけですが、非常に落胆しました。世界五大ウイスキーに分類されるであるジャパニーズウイスキーを海外の模造品と扱き下ろす記事を読んでいると、なんて酷い酒屋なんだろうと思いました。酒造会社のより効率よく、より消費者に求められる酒を作ろうという研究や努力を頭から否定することは、良識ある酒屋のすることとは到底思えません。本場、本物志向の盲目的な分け方はあまりにも粗末でした。
金さえ手に入れればなんでもアリ。という次元からは離れたいんですよね。お客様に自信を持って、旨いし安全だと薦められる商品を増やしてゆきたいという考え方は、とても大事だと思うので本の趣旨に賛同。 お客がアホだから仕方ない、とか、家計が苦しい時代、発泡酒も仕方ない、みたいな方便に逃げずに、自分が酒を扱う哲学を語ってる点が、この本のエライところ。
スポンサーは日本でも評価されれば付きますよ?ヨーロッパでも自分から売り込まなくても勝手にスポンサーになってくれる所はありません。成果、途中経過もちゃんと報告する必要があります。才能勝負の分野はどこの国も似たようなものです。むしろ、若いうちに賞取らないと完全に話にもならないヨーロッパの方が厳しくシビア。ちなみに大抵の人はちゃんと働いてます
職業だけが自己実現の為の回答ではないという意見はなんとなくわかる気がするけど、現実は仕事についてお金を手に入れなければ生活できないのが当たり前で、嫌々仕事するのなら好きなことをやってみればいいということではないのかと簡単に解釈しているのは浅はかだろうか、この本を読んで今好きなことを突き詰めるとこういう道があるのを知っていてもいいんじゃないの?といわれている気がしたのだけれど・・・私だけかな?
多くのビジュアル的に分かり易い、背広を着ない仕事が取り上げられている。薄っぺらな紹介がされている。 そんな中、作家だけは、「何時でも成れるから最初になる必要は無い」これはリアルだ。村上龍の本心であり、軽々しく目指すなと言う意味だ。なら何故他のクリエイティブ系の仕事について、抑制的に書けないのか、おそらくは、取材不足の賜物だからだろう…
記者からの追加情報