ポスト戦後のキャリア論-15 他の国のモデルになれ

|
| 午前4時50分@築地 |
こういう世界は、どれだけ残っているのだろうか――。威勢のよいセリ人の掛け声を聞き、セリ台に立って指で合図して競り落とす昔ながらの風景を見ながら、歴史遺産でも見ている感覚に陥った。隣では、ヨーロッパ人らしき観光客が、モノ珍しそうに見入っていた。日本人の私から見ても、そこには戦後の、昭和の風景があった。
だが、商社が船ごと買って寿司のチェーン店に流すような市場外取引が増え、仲卸業は中抜きされつつある。90年代にウチが2億円弱で買った場内市場の1店舗あたりの権利が、今や500万円の価値しかないという。「市場内の3分の2の店は赤字」というのが親父の見立てだ。市場全体が構造不況である。
経済は効率を求める。地方の商店街がさびれイオンやヨーカドーに置き換わっていくのと同様、築地市場の店も、巨大な流通商社に置き換わっていく。「規模の経済」が働くので、小さい商店主が乱立する「オーナーシップ社会」は崩れ、会社勤めの「サラリーマン社会」へと、どんどん移行していく。この流れは止めようがない。
しかも、小さな町工場の仕事が中国の工場にとって代わられるように、これがグローバル規模で進んでゆく。そうなると、子が親の職業を継ぎたくても、もはや環境が許さない
この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り1,649字/全文2,167字
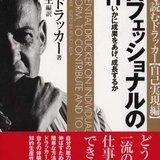
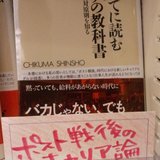
公式SNSはこちら




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報
会員登録をご希望の方はここでご登録下さい
新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)
企画「ココで働け! “企業ミシュラン”」トップページへ
本企画趣旨に賛同いただき取材協力いただけるかたは、info@mynewsjapan.comまでご連絡下さい。