酒文化を壊しているのは政府税制調査会だ
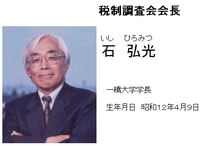
|
| 【官邸ホームページより抜粋】 |
政府税制調査会(政府の諮問機関)の石弘光会長(一橋大学学長)は10月12日の記者会見の席で、発泡酒やビール風酒類について「低価格競争を誘発し日本の酒文化を損なっている」と批判した(『日経新聞』2004年10月16日朝刊)。
この原因が、原料と製法により酒税率に差があることによるならば、(1)酒税率の簡素化。つまり増税してその差をなくし、ビール風酒類の乱発を防ぎたい。
(2)低価格=粗悪酒でビールの味を忘れさせ酒文化を損なわせている。
と、ビールメーカーの姿勢を批判した。
しかし、ちょっとそれはお門違いではありませんか?なぜなら、日本の税制度も採りやすきところから摂るを基本にしており、現在ビールは世界最高税率である。国産ビールの酒税率は大ビン(663ml)当たり41・7%。これはドイツの約7倍、フランスやアメリカの約4倍、イギリスの約2倍である。
その圧制ゆえにメーカーは麦芽の使用量を減らし、税負担が少ない発泡酒扱いで売り出したが、減らした麦芽の代わりに多くの添加物を用いて結果的に不快臭の塊的産物となってもいる。
そこへ追い込んだのは、たび重なる安易な増税を繰り返した税制調査会ではありませんか!発泡酒というマズイ物を生み出させたのも!にもかかわらず、酒文化を損なっているとの発言はいったい何様でしょうか?
庶民がそんなマズイもので我慢を強いられているというのに、その痛みが美食に明け暮れるあなたにはわからないようですね。酒文化云々以前に、酒造りの指針とすべき酒造法さえないでありませんか。苦情を呈す相手は、あなた自身です!
【酒税法と酒造法】
日本には酒税法はあっても、酒造法はない。
明治時代の富国強兵策以来、今日に至るまで日本は、酒のすべてを単なる徴税の道具・手段にすぎないと一貫して位置付け、酒造りの根幹・定義を示すべき酒造法を制定する意志はいまだにない。このため日本は模倣や模造の“天国”と化している。酒文化を確立させる術もないのも、これが大きく影響している。
酒税法は国税庁が1953年に酒税を徴収するためにつくった法律で、酒税の対象になる酒類の定義、課税方式、税率、納税方法、免許制度などを規定している。
ビールを例にいえば、酒税法第三条で「ビール」とは、
<イ)麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの ロ)麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。>
とある。
また、当該政令である酒税法施行令第六条「ビールの原料」には、
<政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類、又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする>
と記されている。1962年の政令施行時には、上記を除く物品(ナツメグ、コリアンダー、オレンジピール、コーヒーなど)は想定外だったため、たとえば果汁、コリアンダーをはじめとする香草などを加えているベルギービールなどは「発泡酒」扱いとされる。
旧来になかった新しいタイプの酒(原料、発酵方法、酵母も異なる酒)の特許権の大半は、醸造試験場が確立させており、その技術を受けてメーカーが商品化する例が多々ある。このため「麦芽・ホップ」のみをビール、「米・米麹」のみを清酒と定義するとなると、いままでの研究・特許を得るまでの努力を全否定することにもつながってくる。
一方、ビール王国ドイツには、「水以外には麦芽、ホップ、酵母の3つの原材料しかビール醸造に用いてはならない」とした「ビール純粋令」という法的な規制がある。
これは1516年、ドイツ・バイエルン地方の君主ウィルヘルム4世が、当時のビールの品質の悪さを憂いてつくった法令で、その後、ワイマール憲法にも採択され、20世紀に入ってもドイツ国内で守られてきた。しかし、第2次大戦後、EC(ヨーロッパ共同体)加盟諸国から「ドイツだけビールの原料を限定するのはおかしい」「非関税障壁だ」と圧力がかかり議会に提訴され、1987年に純粋令は非合法化されることになる。しかし、ドイツ国内の醸造業者は純粋令を守り、伝統のビールを醸造し続けている。技術力・指導力のある第三者の立場の人間が半ば強引に、常識造りの酒造りに戻ることを宣言することがなければ、酒造法も生まれないであろう。酒造法がないのは、消費者の利益を守る消費者保護基本法違反ではないだろうか。




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
ビールの税金は過大すぎるフランス、アメリカ並に10%にしてくれ。
昔の酒の方が、不快臭多かったと思うが。
ブランデーにせよスコッチにせよ、ヨーロッパの酒文化は体制と庶民の確執、つまり税金との戦いの中で生まれました。いわば、庶民と行政の知恵比べの産物が旨い酒とさえ言えます。規制を取り払えば、過当競争を誘発し結果として日本経済に悪影響を与えることさえ危惧されるのでは無いでしょうか?歌舞伎などの庶民文化が規制の中から生まれたように様々な文化と規制が必ずしも文化を疎外するとは思えないのですが。
記者からの追加情報