フリーミアム国家論
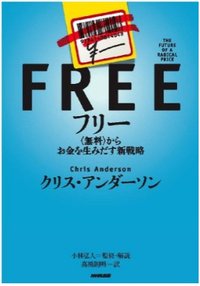
|
自分のビジネスに関係ありそうなので『フリー』を読んだ。気合入れて読んだのだが、概ね既視感。ムーアの法則なんて今ごろ言われても。やはり、本になってる時点で情報が古い。ウェブ触ったことない人向け。
ウェブ上では評価が高いようだが、単価の高い本はアフィリエイトで儲かるからamazon書評家さんたちには「売りたいバイアス」がかかるし、かつ、こういうウェブで売れそうな本は評価が甘くなりがち(そもそも、書評家の言うとおり毎週オススメの本が次々出版されていたら、こんな出版社不況にならない)。
たぶん日米の市場の違いによるところだと思うが、実業の現場で「フリー」と日々戦っている私から見ると、かなりイタい記述が目立った。
まず、この著者はウィキペディアを盲信している。ウィキが、紙とCDロムの百貨辞典市場を縮小させたのは確かだろうが、その先の話がすっぽり欠落。少なくとも日本のウィキはほとんど「2ちゃんねる」と同じで、西和彦氏もいうように、とにかく嘘だらけで信用している人はリテラシーの低い人だけ。まったく実用に値しない。
宮台真司氏も言うように、管理人なき世界では「悪貨が良貨を駆逐する」というのがウェブ世界の本質なのであるが、その点を含め、今後、有料とウィキのポートフォリオがどうなるのかについての論考がゼロ。
もう1つ驚いたのが、1セント払わせるのがいかに大変かというくだり。
|
もうそんなことは分かりきっている。その先を論じないと価値がない。今、ウェブ事業者が取り組んでいる今日的なテーマは、その1セントをどうやって課金すれば、消費者および事業者にとってストレスなくハッピーなのか、という心理経済学に移っている。
有料課金で成功しているのは、日本では圧倒的にケータイだ。どうしてグリーがボロ儲けできるのか。課金されていることを忘れさせるからだ。消費者からみると、薄々知っていても、通話料と合算で請求されるために、心理的に頭に入ってこない(クレジット明細のほうが入りやすい)。
ウェブでクレジット番号を16ケタも入れてもらうハードルと、ケータイでYESボタンを押してもらうだけのハードルの違いこそ、いま論じなければならない。同じ1セント課金でも、最大のギャップは、むしろこちらにある。

|
 |
過去の話をいろいろ分析してノウハウを整理してみたところで、もう古い話だ。時代はケータイとか、心理経済学のほうに移っているんだから、そういう未来の話を読みたかった。
ちょうど一緒に買った「サーカス」で、成毛氏がこう書いている。
|
まったくその通りだ!と思った。「フリー」もハウツー本の一種だろうが、過去の成功モデルを分析して名前をつけてみたところで、既に過去の話に過ぎない。

|
 |
電車のなかで『日経アソシエ』の特集(いつも同じ仕事術ばかり)なんか読んでるイタいサラリーマンをみると、また出版社にカモられてるよ、と可哀想になる。
私も同じ号でインタビューに答えていて、自分の役割を踏まえ、新興国だのケータイだのと真面目に答えてしまったのだが、成毛さんの「もうムチャクチャやるしかないでしょう」のほうが結構、正しいかもしれないので、そっちを読むことをオススメする。さすがこの人、面白い。
■フリーミアム国家を目指せ
ところで、『フリー』に戻ると、じゃあオマエは未来をどう考えるのか、と言われれば、本書を読みながら考えたのが「フリーミアム国家論」だ。基本的な行政サービスは無料で、プレミアムサービスは有料。よい教育を受けたければ、よい医療を受けたければ、プラスα、頑張りなさい、と。

|
 |
これは、ムーアの法則でITコストが下がり続ければ、近未来(10年も経たず)に実現できる。
行政手続きや行政サービスはIT化すれば、大前研一氏が言うようにコストを現状の10分の1にするのはごく簡単だ。既に実現しているように、住民票や印鑑証明などはコンビニで出せばよい。
全国一律のクラウドサービスで、納税も電子申告、選挙は電子投票、公共事業は電子入札、とやっていけば余裕で10分の1だ。困るのは富士通やNECなど利権化しているITゼネコンだけで、国民は全く困らない。
「健康で文化的な最低限度の生活」は簡単で、国民全員にエイサーの低価格PCとADSL接続権を無料配布し、電子図書館を作ってアクセスさせ、勝手にブログでも書かせてツイッターで俳句でも発信させてれば、極めて文化的な生活になる。
問題は「健康で」のところだが、これは生活保護レベルのコスト(1人月15万とか)がかかるから、その分の税収を上げねばならない。そのためには、徹底的な競争戦略、規制撤廃によって、自由競争させ、優秀な人間にとことんまで働かせる。
日本の現状は医療・福祉・農業・教育・建設・通信・電波・再販と規制でがんじがらめなので、優秀な能力が活かせていない。デキる人には死ぬほど働かせて、ガッツリ雇用を作って、ガッツリ納税してもらう。これで国際競争力もつき、輸出も伸び、内需も拡大し、原資ができるわけだ。
このフリーミアム国家論は、ベーシックインカム論に似ているが、私は働くことが賞賛される社会のほうがよいと思うので、負の所得税を課して、働く人ほどよい生活ができる仕組みにする。
つまり、フリーミアムのフリーには2つの意味があって、「無料」の行政サービスと、「自由」な市場競争。それで、プレミアムにも2つの意味がある。行政のプレミアムサービスと、競争優位な人物が自分の稼いだカネで市場で受けられるプレミアムサービス。
問題は、一度、経済が完全に破壊されない限り、既得権がんじがらめの日本でこれが政治的に実現する可能性はゼロということだ。希望は、戦争。または、戦争状態に近いハイパーインフレによるゼロリセット。戦後のように。成毛氏が言うようにハイパーインフレは来そうだから、案外、チャンスかもしれない。



Twitterコメント
はてなブックマークコメント
どうしてグリーがボロ儲けできるのか。課金されていることを忘れさせるからだ。
フリーミアム国家論?:MyNewsJapan編集長、渡邉正裕公式ブログ
全く同感。無料版を読んだが、買ってまで読む価値はないと思った。フリーミアムという言葉を流行らせた(?)事は評価できるが。
facebookコメント
読者コメント
確かにハウツー本で成功なんてみたことないですね。
あと、心理経済学と言う単語をもったいつけたように使いたがる人もあれこれこねくり回した挙句に成功できてないパターンしかみたことないです。
博士か?と。
ハイパーインフレきたらいいねですね。
内向きの闘いばかりしている企業、会社、部署はことごとく駄目だと感じます。本来は外国勢力との激しい競争が起きているのだからパワハラだの個人的な嫉妬感情で人事をいじるだの本当にくだらない事だと感じます。日本経済が完全に破壊されれば日本がかかえる大量の老人さんたちの年金も支払いどころでなくなる可能性もあるでしょうし。老害の高齢者(多すぎる)と既得権益に乗っかった50代にまともな未来を約束する必要なんて20代~30代の方々には不要でしょう。民主党はちょっと色々問題があるのは事実でしょうが公務員や特殊法人関連で少しは既得権益を潰すのに貢献してくれてるようです。もっともっとある種の破壊・革命が必要かもしれません。
記者からの追加情報