トヨタレクサス不買推奨→自主改修→リコール
ちょっと古いが、これは重要なニュース。
13日のロイター。
トヨタのレクサスSUVに横転の恐れ、「不買」推奨=米誌
|
トヨタ、レクサスSUVを改修ヘ 「買うな」報道で即応
|
さらに5日後の読売(4月20日)。
「買ってはいけない」レクサス、リコール
|
消費者団体が、確実に社会に影響力を行使し、トヨタの悪行を未然に防ぎ、消費者の命を救っている。すばらしい。
一方、日本にはこういう独自の実験にもとづき消費者の立場で不買を呼びかけるような消費者団体が存在しない。主婦連は名前からして違うし。かつての『暮らしの手帳』がそうだったようだけど、今はそういう機能を持っている組織が日本にはない。
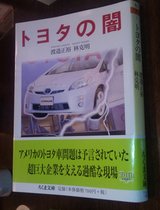
|
5/10発売の文庫版増補改訂。 |
トヨタもさぞかし、ビックリしているだろう。日本でトヨタ車の不買推奨する団体なんて、絶対にありえないのだから。下手すると、非国民扱いされてしまう。トヨタのおかげで日本は持っているのだ!みたいな妄信的なバカは多い。まだ頭が戦後なんだよね。
日本が戦後の開発独裁型の社会から多元的な民主国家にフルモデルチェンジする道のりは、あまりに遠い。
米国でのトヨタ問題の本質が、そこにある。日本にトヨタを止める機能がなかったことが、米国でトヨタを暴走させ、欠陥車で58人殺してしまった。
具体的には、下記5つが機能不全なのだ。
・労組が、御用労組かJALみたいな勘違い労組ばかり。・消費者団体がゼロ。
・政治家が企業と癒着して独立していない。
・行政が企業と癒着して独立していない。
・マスコミにジャーナリズムがない。
そのことを5/10発売の文庫版第6章に追記した。
昨日、見本が出来た。50代の担当編集者は、私が所属していたゼミ教授(草野厚氏)の担当としてちくま新書を2冊出していることが最後に分かった。ああ、そういう縁って何かあるもんだなぁ、と。
ところで最近、出版社の人に会うと、たぬきちブログの話で持ちきりだ。ちくま社内でも回っているそうだ。
たぬきちの「リストラなう」日記
確かに、久しぶりに面白いブログを読んだ。この人は文章力もあるし、フェアな競争環境で戦略的にキャリアを積めば、本人のいう「市場価格」や「同一労働同一賃金」の世界でも、十分通用する人材になりえたと思う。だが、光文社というぬるま湯で40代半ばを迎えては、残念ながら手遅れだ。そういう人が新聞業界やテレビ業界には、わんさといる。つまり、甘い環境に身を置くことで、才能を、人生を、無駄遣いしてしまう人たち。人間は、易きに流れるからね。
講談社は光文社と兄弟会社だが、直接的な資本関係は一ツ橋グループのように深くはないので、救済の見込みもなく、突き放している。
労組が強い講談社は27歳1200万円(40歳1600万円)の給与水準をいまだに維持してるが、破たん直前まで追い詰められた光文社は、その半分の社員平均800万円台にまで削られるという。それでも高いけど。

|
去年の『創』で報じられていた未曾有の危機 |
新書なんて光文社のほうが頑張ってると思うが、スポンサーが関係ないコミック中心か、スポンサー命の女性誌中心か、という違い。能力とか実力とか努力とか、関係なく稼ぎが決まる世界。人材の流動性がないから、光文社でそこそこ仕事ができる中堅社員でも、講談社に転職することはできない。講談社も赤字だから。
まったく今の日本の閉塞感を象徴するような話で、「要は、ほとんどの競争がフェアでないし、失敗した場合のセーフティーネットがしっかりしていないからだ」ということを実感する。まったく同意。
連合のロビー団体と化した民主党政権が、その状況をどんどん悪化させている。
フェアな競争なきところに、経済成長はない。光文社の例で分かるように、破たん状態になるまで既得権は守られる。日本国も、破たん状態になるまで、連合の既得権は守られ続けるわけだ。
ということは、日本全体がいったん、破たん状態になる以外に、日本経済が復活する道はない、ということになる。その前になんとかして全体最適を目指すのが政治家の仕事なのに、ダメ代議士たちは何も分かっていない。これなら、政治家いらないじゃん。
国民は気づき始めているから、参院選で民主党はボロ負けし、また3年は混乱が続くことになる。衆院も同時に解散してくれ、あと3年も選挙できないの?待てないんだけど、というのが国民の本音ではないか。



Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報