『永遠のゼロ』(百田尚樹)が描く人命軽視なブラック企業の起源
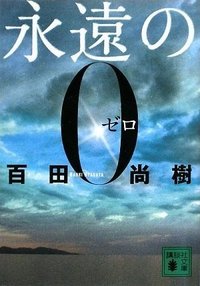
|
| 『永遠のゼロ』 |
僕は常時寝不足なので、買った小説の8割がたは100ページ前後で眠くなり、二度と手に取ることなく捨ててしまう。そんななか、カフェをはしごして8時間ほどで最後まで一気読みしてしまったのが、カミカゼアタック(神風特別攻撃隊)の当事者を主人公として当時の国や家族模様を描いた本書である。小説では『手紙』(東野圭吾)以来の当たりだった。
本作がデビュー作だった百田氏は、持ち込みに際し、大手出版社が軒並み却下し、最後に畑違い(サブカル系メイン)の太田出版が出してくれてダブルミリオン(200万部)突破、というだけでも読む価値がある。大手出版社の文芸編集者がいかに新人を無視し、作品の中身を見る眼が欠落しているか、がよくわかるエピソードだ。
僕がいいと思う小説は、正面から「カ・ド・コンシアンス問題」(悩みに悩んでも正解が得られない問題)をメインテーマとして扱っているもの。サンデル教授の白熱教室のように、答えのない問題を読者に深く考えさせる。自然と人間、環境破壊と開発をテーマとする『ナウシカ』『もののけ姫』も同じ理由でよいフィクションである。
こういう小説は、スカッとしたとか、痛快だったとか、面白かったとか、そういうその場限りの読後感にはならない。心の奥底の(個人的・集合的)無意識に深く残り、人生観に影響を与え、人間を成長・変化させる。
■本書のテーマは特攻隊員の心の葛藤であり、著者自身が「涙を流しながら書いていた」と述べているが、それがどこなのかは、筆致の走りっぷりや感情移入っぷりから、太字になってたりはしないのに、分かってしまう。特攻隊の生き残りに語らせている部分である。そのくらい、著者がこの作品・このテーマに魂を込めていることは伝わってくる。
そこが現代の日本人の心に響き、考えさせ、かつ重要なことなのに何も国が知る機会を与えてこなかったから、需要と供給が一致し、ミリオンセラーなのだろう。何しろカミカゼは、つい60年前、我々のたった2世代前に実際に起きた事実であり、8千人~1万4千人とも数えられる自爆テロ作戦(民間人相手かどうかはどうでもよろしい、同じ人間だ)を仕掛けたのは、世界中で日本人だけという重い現実がある。
911テロなどで自爆攻撃死した実行犯などせいぜい10人といったレベルであり、神国日本に比べたら本当にかわいいもの。その点でこの世界記録が破られることはないだろう。「永遠のテロ」である。
■日本は現在、戦時体制が続いている。『1940年体制』(野口悠紀雄)に詳しいが、税の天引きはじめ現在の社会制度の多くは戦中に考案された。『永遠のゼロ』を読むと、精神構造としても、戦前戦中の軍隊思想が日本中に引き継がれていることが感じとれる。ブラック国家も、ブラック企業も、組織のために人間を使い捨てる点で、根は同じだ。
人命軽視の思想や、赤紙1枚でいくらでも補充がきく兵隊は、ユニクロやワタミで使い捨てられる社員そのもの。たとえば以下は、特攻隊への志願を尋ねる場面だが、「飛行学生」を「ワタミ社員」に置き換えても何ら違和感はない。
記事でも書いたように、ワタミの社員は「ボランティア」の名目で全員がNPO会費を「自発的」に3項目も、給与から天引きされている。入社時に申込みを拒否すると、本社のエラい人から説得を受けるのだという。戦中の軍隊と全く同じである。
僕のなかで、この士官は、勝手に柳井社長を想像して読んでいた。一見すると「自発的」にみえる志願を、実のところ脅迫しているあたりが、「半年で店長になりたくないのか!」「世界で生き残れないぞ!」「泳げない者は溺れればいい」と言っている姿にダブるのだ。
ユニクロの社員は精神的に病んで辞めるケースが多いが、辞めたらまた採用すればいいだけ。「それでもみんなユニクロのために勇敢に戦ったんだね」という感じである。
■桜花(人間ミサイル)、回天(人間魚雷)、ゼロ戦や訓練機によるカミカゼアタック…。近代国家で、自国民をミサイル代わりとした武器を次々と考案し、数千人規模で実行したのは日本国だけだ。日本人は「十死零生」の自爆攻撃を、人類史上ダントツの規模で組織的に行った、世界一自国民の命を軽く扱う、危険な民族だったということを、われわれは事実として知っておく必要がある。その同じ血は今も流れ、日本ならではの「Karoshi」やブラック企業を生み出していると考えられるからだ。
これだけのことをしておきながら国は反省せず、この特攻の状況を詳しく国民に教えてはいない。僕も学校の授業で議論したこともなければ、事実関係を詳しく学んだ覚えもない。本書は、義務教育課程(中学1年くらい)で教材として使用すべきである。様々な参考文献から史実を部分的に引っ張ってきて、つぎはぎしつつ架空の人物にからめているので、全員が読んで議論するのに、かっこうのテーマである。
たとえば本書の文章を、「史実と言える部分」「事実関係で議論が分かれているor証拠不十分な部分」「フィクションの部分」に色分けさせることで、歴史リテラシーの向上も図れる。日本史の現代史、特に戦前から戦中にかけては、現在の日本のかたちの基礎となっているわけで、実際に人材を使い捨てる「ブラック企業」経営者の発想は、全く同じ根からきている。時間を割いて深く理解すべきなのである。
■プロット自体はシンプルで無駄に複雑にしておらず、疲れない。登場人物も無駄に多くない。各生き残り人物に1人称で語らせる構成もいいと思った。あえて改善点を述べると以下2点。①若干、前半が冗長なので、もっと短くしても同じ内容は伝えられる(608ページはやはり分厚すぎる)②フィクションとはいえ、あまりに登場人物を美化しすぎ。著者は「人間の綺麗なところを描きたい」と述べているが、綺麗すぎて現実感が減耗しており、結末に意外性もなく、予定調和であった。
ノンフィクションでは伝えきれない本質を効果的に伝える手法として、小説はジャーナリズムの一形態とも考えられる。50歳までにこうした小説を書けるようになりたい、と思った次第である。



Twitterコメント
はてなブックマークコメント
『MyNewsJapan』(渡邉正裕)が煽る人命軽視なブラック労働の詭弁 https://twitter.com/masa_mynews/status/411493937040207872
社会現象になる創作物は時代を象徴するというが、人の生命や意志を軽視する現代社会に共感する人が多かったからこそヒットしたのかもしれない
作品の批判ではなかった。
雲助に過剰なサービス期待する人がこの記事書くのかーw
精神構造としても、戦前戦中の軍隊思想が日本中に引き継がれていることが感じとれる。ブラック国家も、ブラック企業も、組織のために人間を使い捨てる点で、根は同じだ。 人命軽視の思想や、赤紙1枚でいくらでも補
facebookコメント
読者コメント
ブラック企業への批判を書くために、売れてる小説である『永遠のゼロ』を持ち出すのはやめなさい。他人の褌で相撲を取るな
永遠の0を自分も読み終わりました。見た通り長編でした。もっと短く出来るという渡邊編集長の指摘は最もです。しかし戦争というものや軍部の駄目さ加減を丁寧に描いているのでむしろ適切な長さと感じました。思っていたよりスイスイ読み進めれました。物語に感情移入させる力のあるなしが大きかったのではと思います。
風の中のマリア、影法師も読みましたけど、百田尚樹氏は作風の幅が広いですね。まるで宮部みゆきみたい。
永遠のゼロはずっと売れ続けていますね。
ブラック企業の発想と根っこが実は似ている、近いという指摘は重要ですね。
百田尚樹氏の作品は既に風の中のマリア、影法師は読んだ。
今度永遠のゼロを読んでみます。
永遠のゼロはずっと売れ続けていますね。
ブラック企業の発想と根っこが実は似ている、近いという指摘は重要ですね。
百田尚樹氏の作品は既に風の中のマリア、影法師は読んだ。
今度永遠のゼロを読んでみます。
「永遠のテロ」とは何だ。テロという言葉の原義をわかっていますか。
記者からの追加情報