日本IBM、Lenovo強制移籍600人 THE OTHER IBM(仕事)

|
| 夕刊紙でも「明日は我が身!?」と大きく取り上げられた(2005年2月9日『夕刊フジ』) |
昨年末に発表された米IBMによるPC事業売却は、20代30代の若手社員にとっても「知っている同期が1人くらいは移籍した」という程度に身近な問題だった。
- Digest
-
- 突然、レノボ社員に
- 事業とセットなら“人身売買”が可能な時代に
- 約9割が「労働条件悪くなる」と予想
- 若手もどんどん対象に
- プロフェッションとキャリア
- 定着する専門職制度
- 自律的なキャリア構築を支援
- 教育制度の充実
- トップタレント管理と人材排出
- 離職率は低め
- ワークプレイスのバーチャル化
突然、レノボ社員に
個人業績の良し悪しとは関係なく、会社側のM&A戦略によって、社員がどこに売られてしまうか分らない時代になった。
「知っている同期では、1人行きました」(新卒入社3年目・営業系SE)、「直接の知人は1人。落ち込んでいる感じは受けなかったけど、住宅補助が不安だと言ってました。知人以外を含めても、同期はたぶん2~3人」(30代・間接部門)というように、若手や中堅もかなり移籍している。
従来の「売却」の場合、売られるのは事業だけなので、移籍には本人の同意が必要とされるなど社員の身分は守られていたが、2001年4月の商法改正で創設された会社分割制度による「分割」と、同時に施行された「労働契約承継法」が利用される場合、「主従判定」なるものが行われ、その事業に主に従事していると判定された社員は、事業と一緒に分割されてしまい、本人の同意は全く必要とされない。つまり、「事業と社員のセット移籍」が原則で、社員に選択の余地はない。
今回の分割で「分割計画書」に記載されたのは615人。その時点での退職者は10~20人程度にとどまり、約600人が、2005年4月設立の「レノボ・ジャパン」(聯想集団が100%の株式を所有)に移籍した。従来型の「転籍」者(いったん会社を辞めて再就職)も含め、社員数は640人、雇われ社長には日本IBMのパソコン事業を統括していた向井宏之氏が就任した。つまり、ほとんどが日本IBMの元社員であるが、株主が丸ごと入れ替わったのである。
事業とセットなら“人身売買”が可能な時代に
従来は、会社側の都合による社員の売買は禁止されていたため、身分は変わらないまま売却先の会社に元の会社から「出向」という形がとられることも多かったが、買う側からすれば、人もセットで売って貰って、一蓮托生で自社のために働いて貰ったほうが都合がよい。
売る側としても、いらない事業に在籍していた社員に残られても、他部門ではスキルセットの違いから使い余してしまう。さらに、売られる社員としては、どうせ売られてしまうなら、退職金や年金など積み立ててきたものが引き継がれるほうが有利で移籍の障害が低い。これらの点から、会社分割法と労働契約承継法は、双方の経営側にとって都合が良く、分割(“売却”)交渉はスムースに進むようになった。
分割制度は、組織再編成を簡易かつ容易に行えるようにし、企業の国際社会における競争力をつけるというのがそもそもの目的だったので、経営者にとっては非常に都合がよいものといえるが、働く側から見ると、人生設計が突然、狂うことになる。
確かに労働契約承継法によって、退職金や年金、年次有給休暇などは一応、引き継がれるが、極端にいえば、保証されるのは引き継がれる瞬間だけで、最初の1日でもよい。分割先の企業の経営方針次第で、その後は、いくらでも、どうとでも、条件が変更される可能性がある。「生涯にわたってIBM時代の福利厚生や給与水準を保証しろ」ということになったら、リスクが高くて買う会社などなくなるから、分割制度の主旨から考えても、当然ではある。要するに、最も高いリスクを負うのは社員だ。
「行っちゃったねー、という感じ。この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り8,265字/全文9,720字
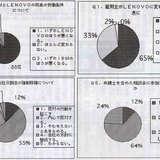
PC事業従事者を対象に実施されたアンケート結果
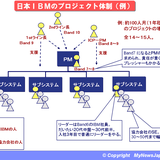
プロジェクト体制例




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
※. コメントは会員ユーザのみ受け付けております。記者からの追加情報
会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい
企画「ココで働け!」トップ頁へ
新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい
サンプル記事をご覧になりたい方は、こちらへ
この記事に関連する情報提供はこちらまでお願いします。info@mynewsjapan.com