サン・マイクロシステムズ

|
 Ba:普通の企業 Ba:普通の企業(仕事2.0、生活4.7、対価3.0) |
例年の流れはこうだ。決算期の6月に業績悪化がクローズアップされ、USの親会社からリストラを命令される。それを受けた日本法人の人事部門がリストラ策を考え、10月に早期退職優遇制度の全体説明会が開かれる。さらに念を押すように、部門長が個別に社員1人1人に対して説明を行う。応募者は人事に連絡し12月ごろには続々と会社を去り始める。
同社のリストラは2001年度から継続的に行われているが、2001年(1年目)の優遇策は、退職金に年収基準額(月額基準報酬×12ヶ月)の6割程度がプラスされるもので、在籍3年以上という条件付きだった。それほど良い条件でもなかったことから(たとえば西友が今年1月に発表した1,500人規模の第3回リストラ策の割増退職金は月収の3~8カ月分だったが、過去2回と比べた貧弱さが批判された)、応募者は100人に満たなかった。

|
20代後半の給与明細 |
2002年は、Sun Globalのなかでも、日本法人のリストラをより強く進める方針が示されたという。しかし、日本では法的に指名解雇が難しい。このため一気に優遇策を充実させ、プラス分を年収基準額2年分強として、年齢制限も完全に取り払われた。つまり、新卒入社1年目でも2年目でも応募OK。USが命令した目標値は、人件費の削減総額ではなく、削減人数だったため、人事にとっては、人件費が安い若手であっても良かったのである。
これを受け、2年目は約100人が応募したという。つまり、2001年に辞めた人は、1年待てば、年収1年半分相当をプラスされたことになるため、悔しい思いをしたに違いない。こうなると、辞め時を迷っている社員のなかには「もう1年待てば、更に優遇されるのでは」という考えが浮かんでもおかしくない。業績が急回復していないことも、社員は現場感覚でわかっていた。
しかし3年目(2003年)の優遇策は、2年目と同じ条件だった。これを知って「潮時か」と思った社員も多かったためか、目標200人に対し、ほぼ目標を達成する200人弱が応募し、続々と辞めていった。
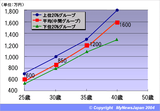
|
年収推移 |
この結果、2000年時点で1400人程度いた社員数は、2001年からの3年間で400人弱が会社を去り、いまや1000人強にまで縮小することに成功している。この間、年間の売上高は1,894億円(2001年6月期)から2年で一気に半減し、950億円(2003年6月期)にまで激減してしまった。
同社のリストラで特徴的なのは、外資の冷徹なイメージとは対照的に、特定のデキない社員を狙い撃ちした「カウンセリング・アウト」(=呼び出して依願退職に追い込むこと)や、「あなたのポストがなくなりました」式の事実上の指名解雇がないことである。皆が平等の条件。その代わり、責任ある立場にいる上級管理職までもが同様に責任をとらない。この間、責任をとって辞めたのは、日本IBM出身の菅原敏明社長(当時)くらいといわれる。
年齢制限をせずに早期退職優遇を行う会社は、日本では稀だ。「早期退職」もなにも、新卒入社組までも対象としているのである。このため、入社した年に退社した社員もいる。応募すると500万円程度は貰えたため、1~2年目に辞めていった社員のなかには、「短期のオイシいバイトだった」という感覚で、第2新卒として就職活動に励む者、とりあえず海外旅行でバケーションをとる者、資金を生かして留学する者などが相次いだ。
年齢制限を外したリストラ策をとらざるを得なかった原因は、2001年頃にITバブルが弾けるまでの数年間、急激な人員拡大路線をとっていたため、20代社員の余剰感が強かったことも影響している。1998年に実質的な日本法人のトップに就任した菅原敏明副社長(99年7月から社長)が「3,000人体制」をブチ上げ毎年200人程度の大量採用を始めたのは、社内では有名な話。「まず人員増ありき」の拡大路線のしわ寄せで人生を狂わされた若手社員の間では、かなりのひんしゅくを買っている。
2003年には、採用数を縮小したものの、新卒約30人が入社。研修を終えて夏に配属が決まったものの、「恒例行事」のリストラが秋にUSトップダウンで決まったため、人事部門は新人に席を与えず「自分で仕事を探すように」などと無理難題を押し付け、そのまま辞めざるを得ない状況に追い込もうとした。配属の撤回である。実際、SE職のトップが新人向けに、その方針を伝える説明会を一回、開いたという。結局、良識あるマネージャークラスの進言によって席は与えられたが、この件は社内に一気に広まり、人事に対する現場の不信感はますます強まった。
人事としてはリストラのノルマを達成するために画策したと思われるが、同社ではもともと人事部門と現場部門が離れていると言われ、現場の実情を省みずに親会社(US)の命令そのままにリストラを進める安直な人事政策を象徴する出来事と捉えられた。同社の要員計画が単純な人数合せを目的としたものであることは、社員研修を担当する人材教育部門を真っ先にリストラしていることからも伺える。現場社員にとって、同社の人事部門は、目先の目標しか頭にない思考停止した親会社のイエスマンと映っている。

|
意思決定カルチャー他 |
こうした不信感も後押しした結果、2001年入社組は、入社3年目の2003年末時点で約半数が辞め、2000年入社(同4年目)組でも、3分の1が会社を去っていったという。
それでも、こうした最悪の状況下で、比較的転職しやすい若手社員が半分以上残っているのは、それなりに待遇が良く、居心地がそれほど悪くないからだ。初任給は学部卒でも初年度500万円程度、院卒では550万~650万円にもなり、外資系企業のなかでもトップクラスに入る。その後、業績が普通ならば、制度上は、20代のうちは2年ごとに年収が1割程度ずつ上がるような仕組みになっている。しかし、2000年に業績が悪化し始めて以降、現在に至るまで昇進・昇格がフリーズしているため、実際には据え置きだ。
この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り4,319字/全文6,791字




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
非常識といえば、社会保険料100%負担てところ。さすがに業績不振なのでその制度が撤廃されることになったら、もっと非常識なことが行われるそうで。本当にお手盛りが好きな会社のようです。復活は難しいでしょうね、特に日本法人は。
サンが最高の時期に在籍していました。リストラ策をとる前に辞め、割増金をもらえませんでした。悲しい。サンの常識は世間の非常識なので、その非常識をいまだに”常識”と思っていますから、日本法人の売り上げが1/3近くに落ち込んでも、営業やエンジニアの現場を知っている者でなく、間接部門の米国のイエスウーマン(マンも含む)がトップに座るような会社です。今後も業績の回復は望めませんね。
Javaがなくなると困るが、ローカライズをちゃんとやってくれれば、日本法人はいらない会社
もう、箱屋の時代は終わりでしょう。一部PCでは成功を収めている会社もありますけど、ユーザのニーズは非常に早く変わっているし、いつでも他社に乗り換えられる時代ですから。
さて、続きです。サンの失敗は、サービスを伴わずにハイエンドサーバを路線を突き進んだ事です。一部がまだ言っているように、『直販の体制を早期に構築しておけば..』と言うのは完全な的外れです。サンはまたローエンドに戻れば良いのです。そして、また喰い上がれば良いのです。その時はスコットが言っていたように、サーバーは、世の中に無いのですから。 サン、頑張れ!
私にとっては、サンは今でも素晴らしい会社です。みなさんは、サンがいなかったIT業界を想像できますか? 開発環境にJavaがない世界を想像できますか?私は自らサンから出て、『外の世界』(揶揄ではありません)を経験してそう思います。私はサンをまだ、まだ、信じてます。
フロントSEの数が無駄に多く、商談や案件の度にぞろぞろ連れてくる様は、遠くからでも分かる程。そのSEも自分の発言が上司や周囲に覆されるからか、真面目?にメモをとるだけ。はきり言って何の役にも立っていません。質問しても回答はユーザの状況を踏まえていないのでチンプンカンプン。1つの質問で数十のやりとりが発生してしまっていました。もはやSEではないですね。
なかなか良い所をついている記事だと思います。チャネルセールスの為、営業が営業らしくない会社です。営業の成績は担当しているメーカーやリセラーやSIerの成績次第。値引きや納期対応等で毎日辟易している担当者を見る度、「この担当者も長くないな」と思うこと然りです。
記者からの追加情報
企画「ココで働け!」トップ頁へ
企画「ココで働け!」の新着お知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい キャリアコラムのメルマガ登録はこちらからお願いします
会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい