読売新聞が批判的なジャーナリストに言論妨害 東京地裁も著作権を拡大解釈、削除命令

|
| 読売新聞本社による販売店イジメを告発した黒薮氏への報復ともとれる今回の削除要求は、報道機関として自らの首を絞める愚かな行為だ |
- Digest
-
- 紛争相手の読売法務室長からの削除要求
問題となったサイトは、黒薮氏の主宰する「新聞販売黒書」 。
紛争相手の読売法務室長からの削除要求

|
| ■催告書(黒塗りは編集部) 12月21日の新聞販売黒書に掲載された回答書を見た江崎氏から、同じ21日に送られてきた催告書。著作権法が拡大解釈されれば、報道には不可欠な資料や文書も将来このように黒塗りされるおそれがある。  |
「発端は2002年頃までさかのぼります。当時、読売新聞社の販売店であるYC広川(読売センター広川)は、読売新聞西部本社から廃業を迫られていました。しかし、同店の店主である真村久三さんは、読売新聞社の申し入れを拒否します。
その結果、真村氏は読売関係者からさまざまなハラスメントを受けるようになったのです。YC広川を訪問して、業務上の打ち合わせをすることすらも中止したのです。『飼い殺し』、あるいは『死に店』扱いと言われる扱いです」
真村氏は2002年9月に地位保全の裁判に踏み切った。そして2006年の9月に地裁で勝訴を勝ち取った。2007年6月には福岡高裁でも真村氏の訴えが認められた。その後、昨年の12月25日に、最高裁判所が読売新聞社の上告受理申し立てを受けつけない決定を下し、真村裁判での読売新聞社の敗訴が確定した。
黒薮氏が続ける。
「最高裁の決定が下る少し前の時期、つまり2007年の12月に入ってから、読売新聞社は真村氏に対して、訪店を再開したい旨を申し入れてきました。真村氏はだたちに、江上武幸弁護士に相談しました。と、いうのもこの時期にはまだ最高裁の判断が下っていなかったために、真村氏は『自分は読売新聞社と係争中である』という認識があったからです。
江上弁護士は読売新聞社の真意を確認するために、内容証明の郵便をおくりました。その結果、法務室長の江崎氏から次のような回答があったのです」
「 前略
読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。
当社販売局として、通常の訪店です。
以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。」

|
| (上から) ■江崎氏の代理人喜田村弁護士が出してきた仮処分命令申立書。江崎氏の催告書をサイト上から削除することを要求している。 ■仮処分命令申立書に対する黒薮氏の答弁書。催告書は著作物にあたらないので申立を却下するよう求めている。 ■喜田村氏準備書面 江崎氏の代理人喜田村弁護士による準備書面。著作者は、読売新聞西部本社ではなくて江崎氏個人であること、は読売による仮判決の申し立ては言論弾圧には該当しないということなどを強調している。 ■江上弁護士陳述書 黒薮氏の弁護士による陳述書。読売側がなぜ今回の仮処分申立を起こしたのかを、真村裁判からのいきさつを踏まえて検証している。 ■江上弁護士準備書面 黒薮氏が弁護団のアドバイスを得て作成した準備書面。著作物とは何かを明快に説明するとともに、江崎氏の回答書も催告書も職務上作成した文書であり、江崎氏個人の創作物などではないと断定している。 ■東京地裁が出した仮処分決定書。主文のみで、本来必要な理由が記載されていない。  |
すると即日、江崎氏から黒薮氏に宛てて催告書が送られてきた。その内容は次の2点に集約できる。
1、江上弁護士に対する回答書は、江崎氏の私的な文章である。
2、著作権法18条1項にもとづいて、新聞販売黒書から回答書を削除してほしい。
「1」について言えば、回答書には「読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です」と肩書きを明記した一文があるうえに、「当社販売局として、通常の訪店です」という明らかに読売新聞・販売局としての見解があり、とても私的な文章とは思えない。
「2」については、回答書の文面は、著作権法でいう著作物には該当しない。著作権法によると、著作物とは「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。
黒薮氏は、念のために江崎氏に同氏が考える著作物の定義などを問い合わせた。しかし、江崎氏からなんの返答もなかった。そこでこの催告書の全文を「悪質ないたずらメールの可能性も?」というタイトルの記事と一緒に新聞販売黒書に掲載したのである。一種の迷惑メール防止策である。
これに対して江崎氏は、12月28日付で「新聞販売黒書から催告書を削除せよ」という仮処分命令申立書を東京地裁に提出してきた。最初に引用した回答書については、削除を要求しなかった。
仮処分命令申立書の江崎氏の代理人は喜田村洋一弁護士。読売新聞社が完全敗訴した真村裁判でも読売側の代理人に名を連ねていた弁護士だ。
◇削除の仮処分命令を下した東京地裁
大新聞の法務室長が傘下の販売店とのトラブルの件で回答した文書に、著作権や公表権が認められるはずがない。筆者を含めた周囲のライターは当初はそう思っていた
この先は会員限定です。
会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。
ログインすると画像が拡大可能です。
- ・本文文字数:残り3,902字/全文6,167字
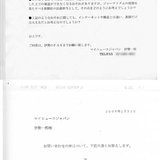
読売に送った質問書と読売からの回答書。今回の裁判では、著作者は江崎氏個人と主張するので、江崎氏への質問として送ったのだが、回答にはわざわざ「読売新聞西部本社広報宣伝部」とある。不可解な使い分けだ。
公式SNSはこちら




Twitterコメント
はてなブックマークコメント
facebookコメント
読者コメント
読売って史上最低の新聞社じゃないですかね。絶対関わりたくないし、こんな会社に広告出してる会社の商品も買いたくない。
喜田村のやり方は、みみっちいのひと言であります。
私も喜田村らしき文面で回答書が届きました。
私は読売暴行被害者の田代裕治です。
ブログ
ココログ で
田代裕治
検索してください!!!
小沢の問題に対してこれぞとばかりに民主のことを書くのであろう世論調査でも他紙と数字が一桁違うのはなぜか与党自民に偏り過ぎじゃないのか国民は見て居るぞ
大企業からの「催告書」を公開することが著作権法違反でできないというのなら、サラ金会社が顧客に送りつけている多種多様な「督促状」や「催告書」の類も、著作物だから公開不可ということでしょうか。
そんなアホな。
名誉毀損をつかった報道対策も露骨にやりすぎて評判が悪くなってきたので、あらたに著作権法を使った批判封じをやってみた。そうお見受けしておりますが、いかがでしょうか。K先生。著作権法は2005年に「改正」になり罰則が強化されています。 動機はともかく、会社はでかいのに、やることは小さいですね。
記者からの追加情報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
読売新聞が自社に批判的なジャーナリストに言論妨害
東京地裁も著作権を拡大解釈し削除命令を出す
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
フリージャーナリストの黒薮哲哉氏が読売新聞から不当な言論妨害を受けています。
その妨害内容は報道に関わる全ての方に影響を与える深刻なものなので、ぜひ多くの媒体で取り上げていただきたいと考え、以下にその経緯をお知らせします。
「読売新聞」西部本社の法務室長江崎徹志氏が傘下の販売店とのトラブルの件で弁護士に送った文書を、 ジャーナリストの黒薮哲哉氏が昨年12月21日に自分のサイト(新聞販売黒書https://www.geocities.jp/shinbunhan bai/)で引用したところ、法務室長から「削除せよ」との催告書が送られてきました。
そこで、黒薮氏がその催告書も掲載し報道したところ、法務室長は著作権を理由に催告書削除の仮処分申立を行い、東京地裁は1月22日にサイト上からの削除命令を下したのです。
そのため、黒薮さんは現在一時的にサイトから催告書の全文を消去しています。この言論妨害行為の読売側の代理人は喜田村洋一弁護士です。
著作権法第2条1項には、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。
この定義に照らせば、読売新聞の法務室長が職務に関して回答した文書が著作物に該当するとは思えません。
しかし、東京地裁の佐野信裁判官は、理由も記さずに「サイトから、別紙の文章を削除せよ」という命令書を出しました。
著作権法を拡大解釈したこのような削除申立が認められれば、内部告発などの資料や文書を提示した上での報道ができなくなってしまう怖れがあります。報道機関であるはずの読売新聞も自分の首を絞める愚かな行為です。
以上のような読売と司法の暴挙に対し、黒薮氏は近日中に本裁判を起こすことを弁護団と検討しています。
ぜひこの事件を、メディア、メール、ブログ、HPなどで 幅広く伝えていただくよう、お願い致します。
2008年2月4日
本文:全約7,100字のうち約4,200字が
会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい
新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)