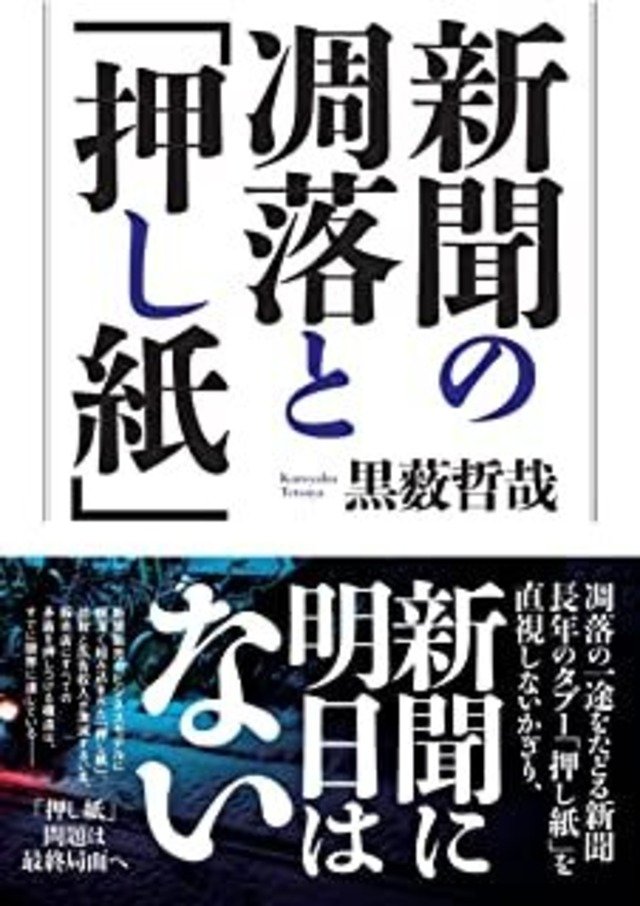新聞の凋落と「押し紙」
「押し紙」問題は最終局面へ
花伝社より発売中2013/7/1発売 黒藪 哲哉=著
第1章 新聞の発行部数が急落している2つの要因
第2章 新聞広告の傾向分析にみる新聞の凋落
第3章 新聞凋落期のメディアコントロール
第4章 「押し紙」問題とは何か?
第5章 「押し紙」の古くて新しい定義
第6章 「押し紙」の歴史と実態
第7章 軽減税率をめぐる議論
第8章 新聞業界が消費税軽減税率にこだわる本当の理由
第9章 新聞凋落の下で進む政界との癒着
第2章 新聞広告の傾向分析にみる新聞の凋落
第3章 新聞凋落期のメディアコントロール
第4章 「押し紙」問題とは何か?
第5章 「押し紙」の古くて新しい定義
第6章 「押し紙」の歴史と実態
第7章 軽減税率をめぐる議論
第8章 新聞業界が消費税軽減税率にこだわる本当の理由
第9章 新聞凋落の下で進む政界との癒着